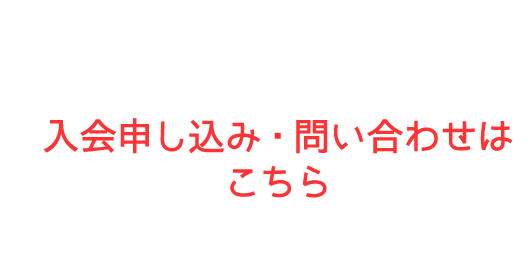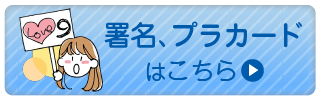新婦人は、3月3日~7日までアメリカ・ニューヨークの国連本部で開催される核兵器禁止条約第3回締約国会議に向けて、声明(作業文書)を提出しました。
核兵器禁止条約第3回締約国会議への声明
2025年2月17日
新日本婦人の会
戦後・被爆80年、日本の核兵器禁止条約参加を
新日本婦人の会(新婦人)は1962年に創立、国連経済社会理事会の特別協議資格を持つ非政府組織(NGO)として、平和と核兵器廃絶、女性の権利とジェンダー平等をめざして活動しています。
ノーベル平和賞受賞を力に
広島、長崎への原爆投下から80年、第二次世界大戦終結から80年の今年、国連憲章や国際法、国際人道法に違反する行動や、軍備増強、軍事同盟強化の動きによって世界は分断され、核使用の危険がかつて高まる危機に直面しています。
危機のなかで、2024年のノーベル平和賞が日本原爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与されたことが運動を励まし、世論に大きな変化を起こしています。被爆者がみずからの痛苦の「体験をとおして人類の危機を救おう」と、被爆証言と運動によって核兵器使用の「タブー」 をつくってきたことを称え、その核のタブーが脅かされる現状への警告として、被爆80年を前におくられたものです。核兵器廃絶を会の目的に掲げ、会員にも多くの被爆者がおり、ともに署名や原爆展などにとりくんでいる新婦人は、今回の授賞をわがことのように喜び合い、運動に弾みがついています。
一方、石破首相はノーベル平和賞受賞に祝意を表しつつ、日本被団協との面会では核抑止力がいかに重要かを主張し、核シェルターが必要とまで述べて批判を浴びました。先の日米首脳会談でも、アメリカの核兵器などによる「拡大抑止のさらなる強化」を打ち出したことは、被爆者をはじめ核兵器のない世界を求める日本と世界の人々の声に反するものです。戦争を放棄した憲法にも違反します。唯一の戦争被爆国日本が、「核のタブー」をこわし、世界を危険にさらすような行動をとることは絶対に許されません。私たちは、戦後・被爆80年の今年こそ核兵器禁止条約に参加を、少なくとも第3回締約国会議にオブザーバー参加をと、政府に繰り返し求めてきました。
核抑止力を打ち破る
地域で自治体との共同も広げながら被爆の実相を伝え、署名を集めて日本の核兵器禁止条約参加を求める世論を高める草の根の運動こそ、核抑止力を打ち破る力です。
今年はすべての地域で被爆者の証言を聞くつどいや、写真パネルや広島の高校生が描いた原爆の絵の展示を開くことをめざしています。高校生が描いた絵を紹介すると、修学旅行の事前学習や平和教育の教材になると各地の高校で歓迎され、小学校や中学校でも展示が実現しています。
自治体にも平和都市宣言や非核都市宣言、日本被団協のノーベル平和賞受賞にふさわしいとりくみをと申し入れ、市役所のロビーや公共施設、図書館などでの展示が広がっています。地方議会で国に条約参加を求める意見書を採択するようはたらきかけを強めています。。
日本政府に条約参加を求める署名は、1月22日で172万3463人分となり、そのうち44万4929人分を新婦人の会員が集めています。署名行動では、小中高生をはじめ若い世代もよってきて署名するなど、どこでもこれまでにない反応です。ノーベル平和賞受賞で日本被団協への注目が高まり、「人類と核兵器は共存できない」「核兵器による安全保障という考え方はまちがっている」という訴えが、これまで以上に共感を持って受け止められていることを示しています。
こうした運動の中で、地元の被爆者や戦争体験者の話を聞いたり、戦争遺跡をたどるフィールドワークなど加害の歴史も学ぶ次世代の会員のとりくみも始まっています。SNSなどあらゆるツールでの発信をつよめ、運動に参加する次世代を増やし、被爆の実相と運動の継承をすすめていきます。
新日本婦人の会は、核兵器禁止条約の普遍性を高めるために、国連女性の地位委員会をはじめあらゆる機会に、すべての国に条約参加を求めていきます。
下記よりダウンロードできます
【声明・英文】Third Meeting of State Parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

.png)